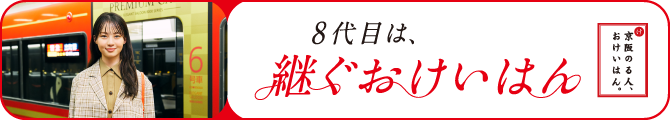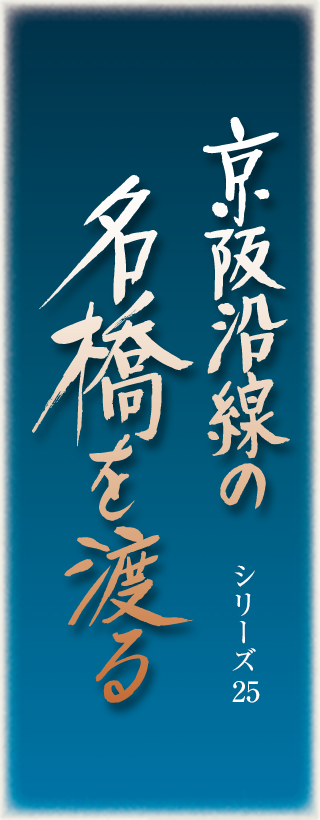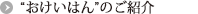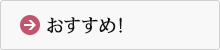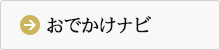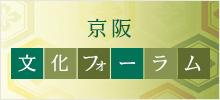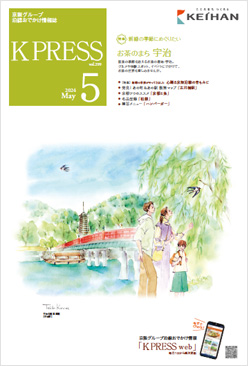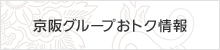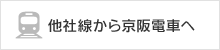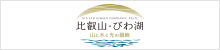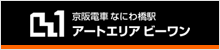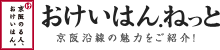京阪沿線の名橋を渡る vol.25
上賀茂神社 橋殿(はしどの)
上賀茂神社の御手洗川(みたらしがわ)に
架かる橋殿は、神域と人間界をつなぐ
「交流の場」だった。若一光司
川や谷や海や池、あるいは道路や線路の上に架けて通路とするための「橋」は、世界のあらゆる地域に存在する。しかし、「橋であると同時に祭祀(さいし)施設でもある」というような建造物は、ごくごく限られた文化圏でしか見られない。
その一つが、日本に古くから存在する「橋殿」である。
橋殿と言えば、「古都京都の文化財」として世界遺産にも登録されている上賀茂神社のものが、特に有名だ。
「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」を正式名称とする上賀茂神社は、平安遷都の以前からこの地に住した賀茂氏の氏神で、神代の昔に本社北側の神山に降臨した賀茂別雷命を祀(まつ)ったことに始まる。678(天武天皇7)年に天武天皇により、現在の社殿の基が造営された。
上賀茂神社の一の鳥居から境内に入ると、二の鳥居へと一直線に延びた参道の両側に、緑の芝生が広がっている。
この芝生広場は、斎王桜や御所桜などの桜が並ぶ花見の名所で、「賀茂競馬(くらべうま)」が執り行われる際の馬場ともなっている。
さらに、長い参道を抜けて二の鳥居をくぐると、正面に細殿があり、その前には左右一対で、純白な砂が見事な円錐形(えんすいけい)に盛られている。これは、御祭神が降臨した神山を象徴する「立砂」と呼ばれるもので、神を招く憑代(よりしろ)である。立砂は厄除けの「清め砂」の起源だ、との説もある。
この立砂と細殿のすぐ右奥で、御手洗川をまたいで建つのが、入母屋造り妻入りの橋殿だ。創建年代は判然としないが、1000年以上前から存在したことは間違いない。
現在の橋殿は1628(寛永5)年に造り替えられたもので、間口が1間(約1.8m)、桁行が5間(約9.1m)の小ぶりな建物だが、桧皮葺(ひわだぶき)の屋根を戴く姿が平安時代の面影を正確にとどめているとして、国の重要文化財になっている。
橋殿の内部には、前方正面の1間分を除いて板床が張られ、両方の側面には高欄の付いた縁が設けられている。
ではこの橋殿は、いったい何をするための建物なのか?
その答えを、1200年以上の歴史を持つ賀茂祭(葵祭)に関する古い文献資料に見ることができる。賀茂祭はもともと、上賀茂神社と下鴨神社(賀茂御祖神社)の例祭だったが、やがて天皇の勅命で行われる国家的な祭祀へと発展した。
この賀茂祭の祭儀において、天皇によって派遣された勅使が御祭文(神仏に対する天皇の御言葉)を奏上する場が、橋殿なのである。そして、御祭文を授けられた宮司は、それを神前に供えた後、橋殿の北側にある神聖な影向石(神の依りつく石)の上に蹲踞(そんきょ)して、神からのメッセージとも言える返祝詞を、橋殿の勅使に向かって奏上する。
この神事が端的に示しているように、橋殿の真下を流れる御手洗川は神域と人間界を区分する「境界」であり、その境界上に建つ橋殿はまさに、神域と人間界をつなぐ「交流の場」なのである。

◆ 出町柳駅からバス 上賀茂神社前下車すぐ
しかも、人が神の意志に触れることのできる特別な場である橋殿は、床下をせせらぐ御手洗川の清浄な水の流れによって、絶えずきよめられ続けている。
一見したところ、それほど注目すべき特徴もないように思える橋殿だが、そこで行われる神事には、格別の意味がこめられていたのだ。橋殿には、神道の根源的な自然観や宇宙観が凝縮されていると言っても、決して過言ではない。
上賀茂神社 橋殿付近をのんびり散策

-

片岡社
上賀茂神社の摂社で、縁結びのご利益があるとして女性に人気。紫式部も参拝したと伝わります
-

久我神社
航空・交通安全の守り神として知られる、上賀茂神社の境外摂社。拝殿は左右にひさしが付く切妻造りです
-

古田織部(ふるたおりべ)美術館
戦国時代から江戸時代初期に活躍した武将茶人・古田織部をテーマとした美術館で、織部ゆかりの茶道具や資料などを展示
-

京都府立陶板名画の庭
古今東西の名画を転写した陶板が屋外に展示された絵画庭園。設計は建築家・安藤忠雄によるもの
-

京都府立植物園
1924(大正13)年に日本最古の公立総合植物園として開園。国内最大級の観覧温室では約4,500種類の植物が観賞できます
![]()
一膳飯屋りぃぼん
いちぜんめしやりぃぼん
フレンチレストランが手掛ける“ちょっぴり大人の定食屋”。オーナーの地元・滋賀県の近江米で作るふっくらツヤツヤの釜飯が絶品です。築約100年の古民家を生かした趣ある空間も魅力。
- 11時30分~14時(L.O.)
17時~21時(L.O.)
水曜(祝日を除く)休業
※予約がベター - 075-723-3329
- 京都市北区上賀茂朝露ケ原町28-20
- 出町柳駅からバス 上賀茂神社前下車 北西へ徒歩約5分


ズーセス ヴェゲトゥス
ずーせす ゔぇげとぅす
ドイツで修業し、国家資格である製菓マイスターを取得した店主が営むバウムクーヘン専門店。できる限り旬の国産素材を使用し、1本ずつ丁寧に焼き上げられています。
- 12時~19時
水・木曜休業 - 075-634-5908
- 京都市北区紫竹下竹殿町16
- 祇園四条駅からバス 下竹殿町下車 西へすぐ


蕎麦屋じん六
そばやじんろく
店主が手打ちする十割そばのお店。そばの実は、福井県を中心に全国10カ所以上のそば農家から仕入れています。産地による風味の違いが堪能できるよう、そばつゆはあえてシンプルに。
- 11時45分~17時(L.O.)
※売り切れ次第終了
月・第4火曜(祝日は翌日)休業 - 075-711-6494
- 京都市北区上賀茂桜井町67
- 出町柳駅からバス 北山駅前下車 西へ徒歩約10分


価格・営業時間・電話番号等が変更される場合がありますので、
おでかけ時には、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

- シリーズ29 下鴨神社 輪橋(反り橋)
- シリーズ28 三井寺 村雲橋
- シリーズ27 指月橋
- シリーズ26 東福寺 通天橋
- シリーズ25 上賀茂神社 橋殿
- シリーズ24 喜撰橋
- シリーズ23 星のブランコ
- シリーズ22 泰平閣
- シリーズ21 水晶橋
- シリーズ20 法成橋
- シリーズ19 流れ橋(上津屋橋)
- シリーズ18 天ヶ瀬吊り橋
- シリーズ17 中立売橋
- シリーズ16 近江大橋
- シリーズ15 第11号橋
- シリーズ14 渡月橋
- シリーズ13 川崎橋
- シリーズ12 社家町の石橋
- シリーズ11 大宮橋
- シリーズ10 淀屋橋
- シリーズ9 七条大橋
- シリーズ8 安居橋
- シリーズ7 梶取橋
- シリーズ6 一本橋
- シリーズ5 難波橋
- シリーズ4 祇園巽橋
- シリーズ3 瀬田の唐橋
- シリーズ2 宇治橋
- シリーズ1 三条大橋