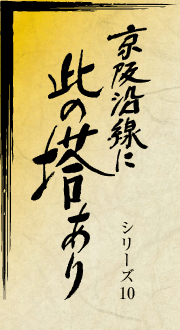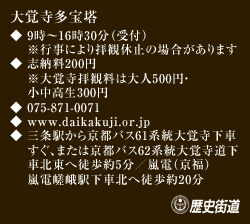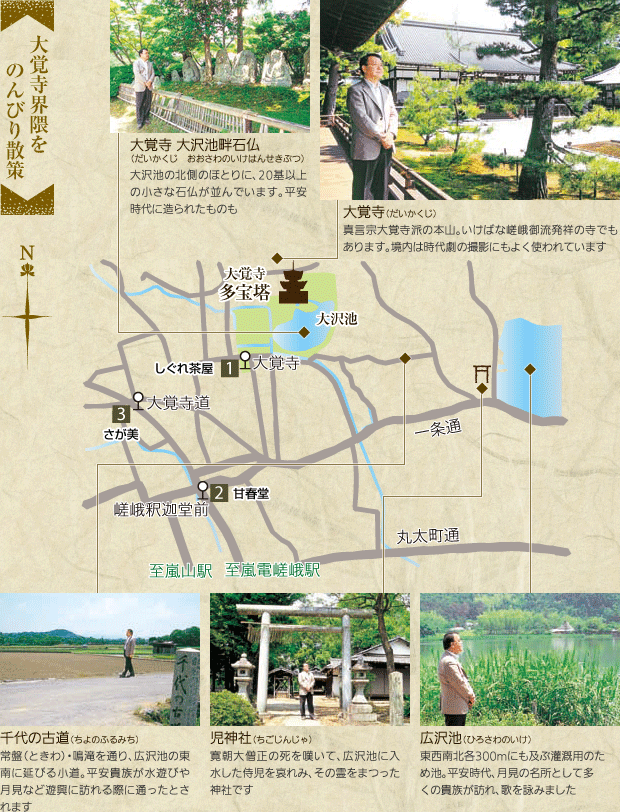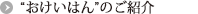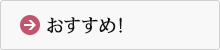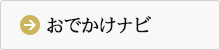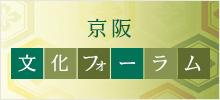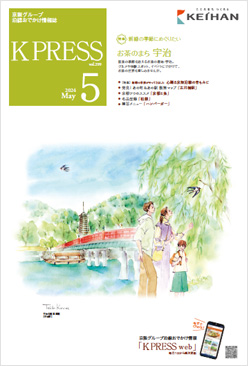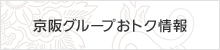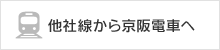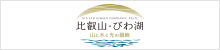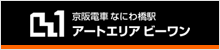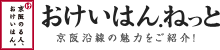1200年以上の歴史を誇る古都・京都には、貴重な文化遺産が数多く残されているが、その大半は戦災や天災で一度は原形を失い、後世になって再建・再造されたものである。
しかし、794(延暦13)年に平安京が成立した当時の趣をほぼそのままとどめている文化遺産も、わずかながら存在する。その代表格とも言えるのが、大覚寺の寺域内にある大沢池だ。
嵯峨野(さがの)の北東に位置する大覚寺は、平安初期に在位した嵯峨天皇の離宮だった。それが天皇の没後に寺に改められ、やがて、亀山法皇や後宇多(ごうだ)法皇による院政の拠点ともなった。そうした経緯から、大覚寺は「嵯峨御所」とも呼ばれ、皇室ゆかりの移築物も多いため、いまも濃密に御所的雰囲気をたたえている。
大陸文化に関心の深かった嵯峨天皇は、唐の景勝地である嵯峨山になぞらえて、この地を「嵯峨」と名づけ、唐の洞庭湖(どうていこ)を模して、大沢池を造らせた。周囲が1kmほどの大沢池は嵯峨院池泉舟遊式(ちせんしゅうゆうしき) 庭園の中核をなす存在であり、日本最古の庭池でもある。
大沢池は古くから、「日本三大名月観賞地」の一つに数えられ、中秋の名月に観月祭が催されてきた。古式ゆかしい龍頭鷁首(りゅうとうげきす)の屋形船が池に浮かべられ、茶席が設けられたりしてにぎわう様は、平安絵巻そのものである。
春は桜、夏は蓮(はす)、秋は紅葉の名所として愛され続けてきた大沢池だが、30数年前には池をめぐる環境の変化により、水草が異常繁茂。その対抗策として、外来の大型淡水魚である草魚(そうぎょ)が放たれたが、草魚はなんと、有用な水草までをも餌食(えじき)にし、ついには大沢池の水草がすべて食べ尽くされるという事態に。
それがさらに、水質の富栄養化や水底の汚泥化などの悪循環を招き、やがて池周辺の樹木の生育にまで、悪影響が及ぶようになった。歴史的な自然系文化財としての大沢池は、まさに危機的状況に陥ったのだった。

そのとき、「草魚を退治して水草を復活させ、周囲の草木も植え直して、1200年前の大沢池の風景を取り戻そう!」と立ち上がったのが、大覚寺と大学(京都嵯峨芸術大学・滋賀県立大学)、それに「いけばな嵯峨御流」の関係者らが三位一体となって結成した、“草魚バスターズ”だった。以後、5年以上にわたって、環境再生のための懸命なボランティア活動が展開され、大沢池は奇跡的に、昔の美しい姿を取り戻した。
その大沢池の景観に見事なアクセントを添えているのが、43年前に建立された大覚寺多宝塔だ。木造風鉄筋コンクリート製で高さ約20メートルのこの塔は、「心経宝塔(しんぎょうほうとう)」と呼ばれ、内部には、嵯峨天皇とも関係の深かった弘法大師の像と、如意宝珠(にょいほうじゅ)の玉を納めた小塔が安置されている。その朱塗りの気高き姿が大沢池の景観と見事に調和し、いつ訪れても、言葉を失うほどの美しさを見せてくれる。
こうして嵯峨の地で、いまも不変のごとき平安貴族の美意識にふれることができるのも、それを護り続けてきた人々の智恵と努力のおかげだと、あらためて痛感させられる。
しぐれ茶屋
しぐれちゃや
昭和初期の茅葺(かやぶ)きの建物を改装した、大覚寺門前の食事処。にしんそばや釜飯などが味わえるほか、わらび餅やぜんざいなどの甘味もそろっています。
にしんそばにわらび餅が付く「あまからセット/950円」

甘春堂 嵯峨野店
かんしゅんどう さがのてん
江戸時代創業の和菓子の老舗。名物・茶寿器(ちゃじゅのうつわ)をはじめ、四季を映した色とりどりの干菓子が並びます。2階の茶房では、上生菓子や抹茶パフェなどが楽しめます。
抹茶に上生菓子と干菓子が 付く「お抹茶セット/630円」 が人気
- 9時~18時 茶房:10時~17時(L.O.)
- 075-861-5488
- www.kanshundo.co.jp
- 三条駅から京都バス61・62系統嵯峨釈迦堂前下車すぐ/嵐電(京福)嵐電嵯峨駅下車北西へ徒歩約15分

価格・営業時間・電話番号等が変更される場合がありますので、
おでかけ時には、ご確認くださいますようお願い申し上げます。